建築基準法上の道路を解説│種類と調べ方、接道義務の基礎知識

建築計画や土地活用を検討する際、避けては通れない「建築基準法上の道路」。建築基準法上の道路に2m以上接していない土地では、原則として建物を建てることができません。
この記事では、建築基準法上の道路がなぜ重要なのか?「接道義務」の基本から、知っておくべき6つの道路の種類(1項1号道路、2項道路など)、具体的な確認方法まで、初心者にもわかりやすく解説します。
建築基準法上の道路がなぜ重要なのか?
原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していない土地には、建物を建てることができません。これを「接道義務」といい、この要件を満たさない土地は、土地活用の可能性が大きく制限されてしまいます。
たとえ接道義務のない「都市計画区域外」の土地でも、道路に接していないと金融機関の融資を受けにくくなることがあり、不動産としての資産価値にも影響します。後々のトラブルを防ぎ、スムーズな計画を進めるためにも、土地購入や建築計画の初期段階で必ず確認することが大切です。
建築基準法42条が定める6つの道路の種類
①1項1号道路(公道)
最も一般的で分かりやすい道路です。国道や都道府県道、市町村道など、普段私たちが利用している公道のうち、幅員4m以上のものが該当します。道路法に基づいて正式に認定されているため、建築基準法上の道路としての要件をクリアしているかどうかの判断が比較的容易なのが特徴です。
②1項2号道路(開発道路)
区画整理事業や大規模な開発行為によって新しく作られた道路です。計画的に整備されているため、幅員や構造が明確で、建築計画を立てやすいというメリットがあります。比較的新しい住宅地などでよく見られます。
③1項3号道路(既存道路)
建築基準法が施行された昭和25年(1950年)11月23日、またはその地域が都市計画区域に指定された時点で、既に存在していた幅員4m以上の道路です。古い市街地などで多く見られます。当時の状況に基づいて認定されているため、台帳での確認が重要になります。
④1項4号道路(計画道路)
都市計画法などに基づき、将来的に新設または変更が予定されている幅員4m以上の道路で、かつ2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路です。計画段階の道路であり、実際に道路として利用できるまでは時間を要することがあります。
⑤1項5号道路(位置指定道路)
道路法や都市計画法によらず、個人などが築造した道路で、政令で定める基準に適合し、特定行政庁からその位置の指定を受けたものを指します。「位置指定」を受けることで、建築基準法上の道路として認められます。
⑥2項道路(みなし道路)
最も注意が必要な道路です。建築基準法が施行された時点などで既に建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したものを指します。
この道路に接する土地に建物を建てる際は、基本的に道路の中心線から2m後退して建物を建てる「セットバック」が必要になります。セットバックした部分は、敷地面積から除外されるため、実際に建物を建てられる範囲が狭くなることに注意が必要です。セットバックによって、当初想定していたよりも小さな建物しか建てられなくなる可能性もあります。
建築基準法上の道路か確認する方法
土地の購入や建物の新築を検討する際は、必ず道路の種類を確認しましょう。ここでは、道路を調べるための3つの方法をご紹介します。
①オンラインでの確認
多くの自治体は、ウェブサイトで「指定道路図」を公開しています。手軽に調べられる便利な方法ですが、データが最新ではない場合もあるため、最終的な確認は役所の窓口で行うようにしましょう。
②役所での直接確認(最も確実)
最も確実な方法は、管轄の自治体の建築指導課や道路管理課に直接出向いて確認することです。担当課では、より詳細な道路情報や、建築基準法上のどの種類に該当するかなど、正確な情報を得ることができます。
③現地調査による確認
自治体窓口で得た情報と合わせて、実際に現地で道路幅員を測定することも重要です。特に古い道路や2項道路の場合、図面上の情報と実際の状況が異なるケースがあります。
敷地境界線が不明瞭な場合は、土地家屋調査士などの専門家に依頼することも検討しましょう。
まとめ:スムーズな建築計画のために道路確認は必須!
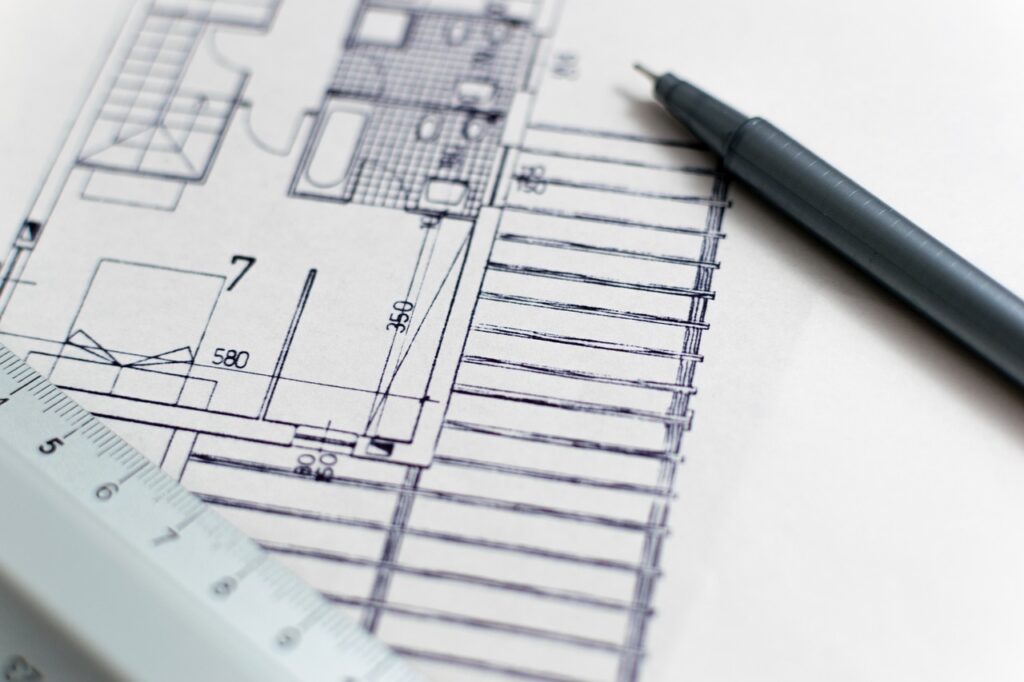
建築基準法上の道路は、建築計画の成否を左右する非常に重要な要素です。土地の購入や建築計画の初期段階で、必ず道路種別と接道状況を確認することをおすすめします。特に、2項道路(みなし道路)に接する土地の場合は、セットバックによる敷地面積の減少を考慮に入れた計画が必須となります。
建築基準法上の道路に関する正確な理解は、スムーズな建築計画の実現と、将来的な不動産価値の維持、そしてトラブルの防止につながります。不明な点がある場合は、建築士や土地家屋調査士などの専門家への相談も検討してください。
💡POINT
- 建築基準法上の道路に2m以上接していることが原則必須
- 道路種別によって建築計画に与える影響が大きく異なる
- 土地購入前や建築計画初期の事前の確認と調査が最も重要
- 特に2項道路(みなし道路)の場合はセットバックに要注意
▼法令はこちら
建築基準法第41条の2
(適用区域)
第四十一条の二 この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
建築基準法第42条
(道路の定義)
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路
二 都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路
三 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)



